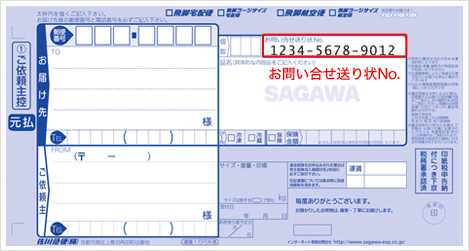1969年、セイコーのクォーツ式腕時計アストロンの発表に端を発するクォーツ革命の打撃から立ち上がり、1980年代なかばに復活ののろしを上げたスイス時計業界。機械式時計の復権が徐々に現実味を帯び始めた1990年代は、まさに試行錯誤の時代であったという。当時の時計業界をよく知るNH WATCH代表の飛田直哉氏は、ブランドの立場からこう振り返る。
「私がこの業界に入ったのが、ちょうど1990年。そこから5年間、日本デスコという代理店でセールスの仕事に従事していました。その頃の日本デスコでは、オーデマ ピゲ、ジャガー・ルクルト、エテルナ、モーリス・ラクロアのほか、ハイエンドなクロックなどを扱っていましたが、高級時計の購買層や売れ方も今とはだいぶ違っていて、100万円を超える時計が店頭に並ぶ機会はあまりなく、百貨店の外商で売られることがほとんどでした。当時、売り手も買い手も共通して思い浮かべる高級時計のイメージは、ダイヤモンドがぎっしり埋め込まれた18金の時計だったはずです。ロイヤル オークに関しては、日本ではステンレススティール×イエローゴールド製の小ぶりなクォーツモデルが好まれていました」
ADVERTISEMENT
多くのメーカーが実直なものづくりだけでは時計製造の文化を守ることができない現実を目の当たりにして、各社が本格的に取り組んだのが、新たな経営スタイルやマーケティングの戦略だった。この話題を語るうえでの欠かすことのできない人物が、IWC、ジャガー・ルクルトを再建し、A.ランゲ&ゾーネを復興に導いたギュンター・ブリュームライン、のちにマーケティングの天才と評されるジャン-クロード・ビバーなど、時計をこよなく愛するカリスマたちだ。彼らが業界で頭角を現したことで高級時計の世界における経営戦略は様変わりした。このような流れと並行して日本の高級時計市場も年々成長を遂げ、世界有数のマーケットとして一目置かれるようになる。
「1994年に日本シイベルへグナー(現DKSH ジャパン)に入社した頃、スイス時計業界は日本の市場を無視できない状況になっていて、さらには今の時代にもつながるヒット作が次々と誕生しました。たとえば、私たちがセールスを担当したブレゲ タイプXX アエロナバルのステンレススティールモデルは、1995年のバーゼルワールドでサンプルを見た途端、必ず売れると確信しました。この前後で、高級時計の古い慣習を打ち破る、いわゆるデカ厚時計の始祖となる時計がいくつか登場しています。振り返ると、90年代は“胎動の時代”だと言え、この時代に起きたさまざまな出来事が今日の高級時計ブームの礎になっているのだと実感できます」
飛躍的な発展を遂げた日本のヴィンテージ市場
日本が世界有数の時計マーケットとして一目置かれるようになったその背景には、1980年代後半から90年代にかけて起きたヴィンテージウォッチブームがあった。1989年にケアーズを創業する数年前から、川瀬友和氏(現ケアーズ会長)はヴィンテージウォッチのディーラーとして、アメリカを奔走する日々を送っていた。
「あの時代は英語も話せなければ、時計の情報すらあまりなくて、何もかもが手探り状態。カリフォルニア州のサイプレス、ローズボール、ニューポート・ビーチ、それから競馬場から大学と、フリーマーケットを回ると必ず時計が売られていました。すでにアメリカでは時計を収集することが趣味として広まっていて、ディーラー、コレクター、ブローカー間でのトレードが盛んでした。ただ残念なことに我々日本人はマイノリティな存在でしたから、仮にいい時計が並んでいたとしても相手にしてもらえないときもあり、そのなかで買える範囲の時計を楽しんでいました。ところが、時計専門誌『タイムスペック』を見ながら卸先の時計店を探していたところ、神田にある骨董館のなかに文明館があると知り(のちに青山のキラー通りに移転)、来店したのですが、これまで自分が見てきた時計とあまりにもレベルの差があったことは、相当なカルチャーショックでした」
「ジム・クラウスという人物との出会いをきっかけに、私たちはハイクラスの時計を扱うショップへと一気に飛躍します。彼は特別なコネクションを持っていて、日本では見ることさえできなかったモデルの仕入れができるようになったからです。1990年代初頭、日本のヴィンテージ専門店でよく売れていたのは、戦後のアメリカで流行した角金と呼ばれる金張りの角型時計。市場が成長すると、オメガ シーマスターやチューダーの通称デカバラと呼ばれるロゴマークのモデルに人気が集中するようになりました。後者はリダン(書き直し)されたダイヤルが無数に出回っていたのですが、それらも含めて、とにかく売れていましたね」
川瀬氏同様、日本におけるヴィンテージウォッチ黎明期を支えたジャックロード創業者・中山直人氏も思い出深い時計とともに当時を振り返る。
「当時(1987年のショップオープン当初)は、ブローバなどの角金時計の取り扱いがメイン。アメリカで安く仕入れることができたので、相場よりかなり安く店頭に出せました。それから徐々にロレックスの比重が増えて、幅広いモデルを取りそろえるように。全般的に売れていたのですが、特に手巻きのオイスターデイト Ref.6694はかなりの数が売れたと思います。私も好きで何本も買い集めていた時計です」
1990年代前半になると、ポール・ニューマンダイヤルの人気に火がついたことをきっかけにコスモグラフ デイトナにブームの兆しが見えて、このほかのプロフェッショナルモデルも注目を浴び始める。
「話題の中心は、ポール・ニューマンダイヤル。扱い始めた頃は120万円前後で販売していて、今の相場と比べれば格安に感じるかもしれませんが、サブマリーナーなら20万円台で十分に買えましたし、当時のヴィンテージウォッチではトップクラスの値付けでした。それからしばらくして、おそらく雑誌の影響からヴィンテージ全般の勢いが一服して、現行モデルとの人気が逆転します。ちょうどこの時期、俳優の木村拓哉さんがドラマで着用したエクスプローラー Ref.14270の相場が2倍以上に上がって社会現象を巻き起こすほどのブームになりました」
ADVERTISEMENT
1990年代のジャックロードの店頭では、ロレックス以外にもオメガ、タグ・ホイヤー、チューダーなどのブランドが売り上げを支えていた。
「我々は商売ですから、買い付ける時計はより売れる可能性が高いアイテムを選ぶのが基本です。オメガやタグ・ホイヤーは、今とは売れるモデルやテイストが違っていました。たとえば、スピードマスターは今のような認知度はありませんでしたし、シーマスターのほうがはるかに人気がありました。チューダーの場合は、一部のロレックスのようなプレミアムがつくことはありませんでしたが、コンスタントに売れていた印象があります。全般的に言えることは、名の知れたブランドの時計を手に入れたい、あるいはファッションアイテムとして時計を楽しむという傾向が強かったと思います。大流行したスウォッチが、このニーズに沿うと感じられたので提案したことがあります。それとは逆に、よりマニアックな時計を求めていた年配の方に支持されていたのがパテック フィリップのRef.96。このモデルも根強い人気がありましたね」
数に限りがあるヴィンテージウォッチの仕入れは、年を追うほどに難しくなる。そこをカバーするために、中山さんはトライ&エラーを繰り返しながら次のヒット商品を探し続けたという。
「1993年に復興したパネライが日本に入ってきた当初はセールスが厳しかったのですが、2000年代に世界的に評価されて、あれよあれよという間にブレイクしたのを今でも覚えています。どの時代もそうですが、次に人気が出る時計を探すことは簡単ではありませんが、だからこそおもしろい。たらればの話になりますが、ロレックス エクスプローラーⅡのように、1990年代末から2000年代にかけて、今ほどは人気がなかったモデルで個人的に買っておけばよかったと思えるものがいくつもありますよ」
経年変化の差を明らかにすることで新たな価値が生まれる
改めて1990年代の日本市場を俯瞰すると、この時代を象徴する時計として、ロレックスのプロフェッショナルモデルを外すことはできない。当時のブームが生まれるきっかけとなったコスモグラフ デイトナのポール・ニューマンダイヤルを筆頭に、90年代と今ではセカンダリーマーケットでの評価基準は驚くほど変化している。その道に明るいコミット銀座の執行役員 兼 鑑定士、金子 剛さんは見解を述べる。
「ひと昔前ならヴィンテージ ロレックスであっても見るからにきれいな状態が人気があって、“トロピカルダイヤル”などの専門用語が飛び交うようになったのは、ここ数年のことです。1990年代に新品で販売されていた5桁のリファレンスも次世代のヴィンテージとして話題になってきはじめており、発売から20~30年近く経過していることから、当時にはなかった経年変化を楽しめる個体が見つかります。ほかにもコスモグラフ デイトナ Ref.16520のように、マニア間でのディテールの研究から評価基準の細分化が進んでいるモデルが増えています」
ADVERTISEMENT
試行錯誤の連続だった1990年代は、同時に昨今の世界的な高級時計ブームの萌芽が見られる時代だった。インターネットの発展から情報共有のスピードが変わったことで世界は一変し、新興の富裕層や投機目的の客層が増えたことで市場規模はかつての数倍に膨れ上がり、いまや一部の時計はアート作品に近い所有価値を持っている。
この結果が、1980年代に先人たちが思い描いた理想の未来なのかは分からないが、確実に言えることがある。それはかつてかつて日本で起きたヴィンテージウォッチブームが、世界でも最も厳しいといわれる日本のコレクターたちの審美眼を培ったということだ。前出の川瀬氏はこう語る。
「(ヴィンテージウォッチブームの)当初は実用的かつ手ごろな値段で買えたことがあって、ロレックスのオイスターデイト Ref.6694が売れ筋でした。正常に作動しようとしまいとお構いなしに1本でも多く時計を集めることに熱中していたアメリカのコレクターに対して、日本ではあくまで実用品としてのヴィンテージウォッチが主流。ですから正常に作動しない時計だとクレームが出てしまうので、小売店では保証が付けられるようになったのです。当たり前のような話に聞こえるかもしれませんが、当時はそうではありませんでした」
1990年代後半に差しかかると、マーケットが成熟していくにつれて、ヴィンテージウォッチの評価基準も変わり、市場から淘汰される時計が出始めた。これについて、氏は次のように述べる。
「アメリカでは徐々に個体のオリジナリティが重視されるようになり始めて、リダンされたダイヤルの評価が下がり、買い取りになると二束三文。そうなると、日本でも店舗での取り扱いが厳しくなるわけです。単純に不人気であるという理由から今では忘れ去られてしまった時計もたくさんあります。1990年代は玉石混交のマーケットでしたが、極端なプレミアム価格では売られていなかったので好きな時計を選びやすかった。その意味でも純粋に時計を楽しみたい人たちにとっていい時代だったと思います。私もそのなかのひとりで、数々の素晴らしい時計と出合う機会に恵まれました」
日本のヴィンテージウォッチブームを支えた伝説的時計ディーラーたち
日本を席巻したヴィンテージウォッチブームを支えた時計ディーラーのひとりに、故・益井俊雄氏がいる。その世界では知る人ぞ知る人物だが、時計愛好家といえども彼を知る人はそう多くない。そんな彼は2022年2月、人知れずこの世を去ってしまったが、彼の時計ディーラーとしての足跡を辿ることで日本のヴィンテージウォッチブームの様子がより明確に理解できる。
1950年、島根県浜田市に生まれた益井氏。都内の大学を卒業後、いくつかの会社で仕事をするも、会社勤めが性に合わなかったという彼は、心機一転、貿易の仕事を志してアメリカ・ロサンゼルスに渡った。1981年2月のことだ。海外雑貨はまだまだ高価だったが、当時の日本では『ポパイ』などの雑誌がこぞって西海岸カルチャーを紹介していたころで、アメリカのファッションや雑貨に対する憧れが非常に強かったという。そこで彼が最初に思い立ったのが、フリーマーケットで古いミシンやタイプライターを仕入れて日本で売るという商売だったが、そこで出合ったというのがブローバの時計に象徴される、いわゆる“角金”と呼ばれるヴィンテージウォッチだ。当時、フリーマーケットにはブローバをはじめとするアメリカの時計ブランドが1930〜60年代にかけて製造したその手の時計が山ほどあったという。そこで益井氏は毎週末になると各地で開催されていたフリーマーケットを回り、この角金時計を買い集めた。
「当時のフリーマーケットでは、箱付きの未使用品がまとまって見つかることも多かったんです。価格もすごく安くてね。そうやって古い角金時計を50本以上も買い集めました」 と、益井氏は以前の取材で語っていた。彼が帰国を果たしたのは、最初の渡米から3年半以上たった1985年のこと。このとき持ち込まれた多くの角金時計はあっという間に完売した。こうして益井氏はロサンゼルスを拠点に、時計ディーラーとして本格的に活動を始めた。ローズボールフリーマーケットをはじめ、ロングビーチ・アンティークマーケット、パサデナ・シティカレッジ・フリーマーケットなど、週末ごとに開催されているフリーマーケットを回りながら、角金時計を買い集めた。それらは平均で30ドルで仕入れることができオーバーホールには約30ドルかかったが、日本ではかかったコストの倍以上で売れたという。
角金時計はいくらでも仕入れることができたが、ビジネスが大きくなってくると、より単価の高い時計が必要になるのが必然。しかしフリーマーケットには、ロレックスなどの高級時計はあまり売っていなかったという。一体どこに行けば、目当ての高級時計を買うことができるのか。そんな折に日本の時計ディーラーたちがたどり着いたのが、NAWCC(National Association of Watch &Clock Collector, Inc.)の存在だった。NAWCCは、1943年に時計師のL.D.ストールカップ(L.D.Stallcup)氏がニューヨークの時計学会でメンバーに声をかけたのをきっかけに発足した非営利団体である。当初は50の支部を持つ団体としてスタートしたが、現在までに52カ国で170の支部が設立され、2万1000人の会員を擁する一大組織に発展した。日本にも第9支部(東京)、第108支部(セントラル東京)、そして第131支部(大阪)と、3つの支部がある。NAWCCの会員になる最大のメリットは、会員制のショーに参加できることだ。本来は商談目的ではなかったが、そこには全米中からコレクターや時計ディーラーが参加しており、フリーマーケットでは目にしたことがないような時計や、時計のパーツなどが数多くそろっていたという。しかも価格が非常に安く、まるで宝の山のようだったと、益井氏はNAWCCのトレードショーの思い出をかつて語っていた。
夢中で全米中を駆け回った買いつけの日々
NAWCCによるトレードショーは、さまざまな州で開催されており、だいたい3泊4日の日程で月2回ほどのペースで全米を回る。そこに出入りしていた日本人は益井氏だけではなかった。時を同じくして、そのトレードショーに出入りをしていたのが元シェルマン代表の磯貝吉秀氏、そして数々の珍しい時計を日本に紹介した仕掛け人といわれている藍川博喜氏(故人)だった。当初はそれぞれ面識はなかったそうだが、当時のNAWCCで日本人の存在は珍しく、彼らはすぐに顔見知りに。特に3人は同い年だったこともあって気が置けない友人として、よく一緒にフリーマーケットやトレードショーを回ったという。
前出の磯貝氏はトレードショーの思い出を次のように語る。
「益井さんたちとは本当によく一緒にいましたよ。ショーが始まる前にホテルのロビーで待ち伏せして、時計を見せてほしいとホテルに着いたばかりのディーラーに詰め寄っていち早くチェックしたりね。そうやっていい時計をショーの前に押さえることがよくありました。あるとき、フロリダ州オーランドにあるフロリダ ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートの近くでショーが開催されたことがあったんですが、当然観光地ですから周りにはディズニー目当ての親子連れがたくさんいるんですよ。そんななかで、僕らだけでなく強面(こわもて)のおじさんたちが観光もせずにディーラーを捕まえて1日中ホテルのロビーに張りついて時計を見ているのが不思議だったのでしょう。“ママ、あのおじさんたちは何しているの?”と小さな子どもにけげんな顔をされたこともありました」
基本的に、磯貝氏はパテック フィリップ、藍川氏はロレックスのバブルバック、そして益井氏はさまざまなブランドのクロノグラフや、ロレックスのプロフェッショナルウォッチ(スポーツモデル)などを商売にしており、それぞれ目当ての時計がうまい具合に異なったそうで、仲のいいディーラーはそれぞれの好みに応じた時計を見せてくれるようになったという。あのディーラーがこんな時計を持っていた、今日はこんな時計が買えたと心を弾ませながらヴィンテージウォッチを買いつけていたと、磯貝氏は当時を懐かしむ。
前出の川瀬氏も益井氏をよく知るひとりだ。当時は旅行会社のツアーなどはなく、どうやってフリーマーケットに行けばいいのかすらわからない状況だったというが、川瀬氏はボロボロのレンタカーと分厚い地図を頼りになんとかアメリカのフリーマーケットに行くことに。
「ローズボールのほかにもサイプレス、ニューボートビーチ、バーストーなど、いろいろなフリーマーケットに行きました。そこには必ず時計屋が出展していました。やったー! って意気揚々とお店に行くと、たくさんの時計が並んでいるなかで裏返しになっているものがいくつかあるんです。理由を尋ねると、“これはケンジがHoldしているんだ”って言うんですよ。それもひとつのお店だけじゃなく、行く先々で。“これはケンジのだ”と。“ケンジって誰なんだ? どういう人なんだろう?”と悔しい思いをしたことを覚えています」
実はこの“ケンジ”を名乗る人物こそ益井氏だった。本名はトシオだが、アメリカではなじみにくい発音だったようで、彼はアメリカでケンジを名乗っていたのだ。行く先々で自分よりも先に目当ての時計を押さえている日本人がいる。その人に負けないように、必死になって自分もいい時計を買えるようになろうと奮い立たせてくれた人物であり、憧れの存在だったと川瀬氏は彼との思い出を話す。
クォーツウォッチが全盛の時代にヴィンテージウォッチの持つユニークなデザインや、ムーブメントの美しさに価値をみいだし、日本に持ち込んだのが彼らをはじめとする時計ディーラーたちだった。そして磯貝氏や川瀬氏はフリーマーケットやトレードショーで山のようにあった時計のパーツも一緒に買いつけ、ヴィンテージウォッチに新品の時計と同じような修理保証をつけて実用品として売り出したのである。世界的にも極めて異例の試みだったが、こうした取り組みによってヴィンテージウォッチは日本で市民権を得ていくこととなった。
バブル景気に沸いていた1980年代後半から90年代初頭の日本。その勢いのままに多くのヴィンテージウォッチが日本に持ち込まれた。ブームの当初は角金時計や、ロレックスのオイスターデイトが人気だったのは前述のとおり。ほかにもデイトジャスト、バブルバックなども人気だったが、サブマリーナーなどのダイバーズウォッチは当初、時計をガシガシ使いたい人がそれこそ本当に水に潜る目的で買うようなニッチな存在だったという。当時はリューズガードつきの高年式モデルのほうが価値が高く、今でこそリューズガードのない初期のサブマリーナーはコレクターズアイテムとして数千万円の価格で取引されることも珍しくないが、当初は単なる型落ちのサブマリーナーとして扱われ、800ドルほどで買えたらしい。夢のような時代である。
関連商品:https://www.jpan007.com/brands-category-b-7.html